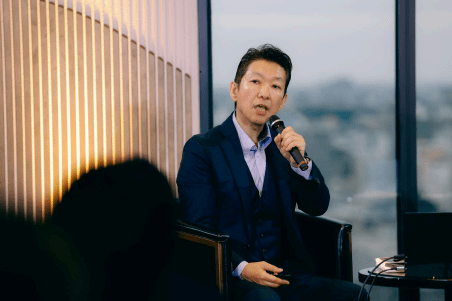
株式会社リコー ESGセンター ESG推進室 室長 羽田野洋充氏
環境経営を軸に、持続可能な社会の実現を目指す株式会社リコー。同社は1998年から環境保 全と利益創出の両立を掲げ、その取り組みを進化させてきました。日本を代表する環境先進企 業である同社は、どのようにサステナビリティを事業戦略に取り入れ、非財務価値を財務貢献へ と結びつけてきたのでしょうか。
本記事では、2024年10月25日に行われたEcoVadis World Tour Japan 2024で、リコーのESG センター ESG推進室 室長である羽田野洋充氏と、エコバディス・ジャパンのメンバーシップアカ ウントマネージャーである佐藤祐也が対談した内容をもとに、同社が長年培ってきたサステナビ リティ戦略の推進方法や、「将来財務」という新しい概念について詳しくご紹介します。
「三愛精神」に基づくサステナビリティ理念
御社の事業内容やサステナビリティ推進の理念について教えてください。
羽田野氏:リコーは1936年に創業した、オフィス向けの複写機やプリンターといったハードウェア を主力とする企業です。近年はデジタルサービスへの転換を目指して、ITソリューションやDX(デ ジタルトランスフォーメーション)にも力を入れています。
当社が企業理念として、創業時から大切にしているのが「三愛精神」です。「人を愛し、国を愛し、 勤めを愛す」という言葉で、事業を通じて、周囲の人々や地域社会、働く現場を豊かにすることを 目指す考えを表しています。この精神は、国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の理念と も通ずるものがあり、社会課題解決に向けた事業はリコーのDNAとして重要な取り組みとされ
てきました。社内調査では、社員の98%が「自分の業務とSDGsが繋がっている」と回答してお り、この理念が社員一人ひとりの行動指針として深く根付いていると私たちは考えています。
環境保全と利益創出への挑戦
環境経営に本格的に取り組み始めた当時の状況や課題について教えていただけます か?
羽田野氏:1998年に経営トップが「環境保全と利益創出の同時実現」という環境経営の理念を掲 げました。しかし、当時は環境保全と利益創出は相対するものと考えられており、社内でも利益 の一部を社会貢献として環境保全に充てれば十分だとみなされていたのです。
この状況を変えるため、環境保全を企業の成長に結びつける仕組みの構築が求められました。 まず、生産拠点での歩留まり向上に注力し、不良品を減らすことで資源ロスやエネルギーの無駄 を削減。同時に、利益の確保にもつながる成果を上げました。こうした取り組みによって、環境経 営の意義を社内に示していったのです。
さらに、全社的な取り組みを加速するため、目標管理制度の改革にも着手し、従来のバランスト・ スコアカードに「環境保全」の視点を加えた5つの評価軸を1999年に導入しました。これにより各 部門の意識が高まり、どう推進していけばよいのか、と我々環境推進部門に相談が寄せられる ようになったのです。そこで、各部門と協力してKPIを設定しながら、環境経営の推進を浸透させ ていきました。

環境経営を全社に浸透させるために、経営層や事業部門をどのように巻き込んできたので しょうか?
羽田野氏:当社の場合は、事業部門長に浸透させることが課題でした。部門評価に環境保全の 視点を取り入れる仕組みだけでは不十分で、特に財務的な視点を重視する部門では理解に時 間がかかることもありました。
そこで、そうした事業の部門長には社内外で環境経営について発信してもらう機会を積極的に設 けました。例えば環境系の取材や広告記事への対応を依頼することで、環境経営について考え たり、必要なレクチャーを受けたりする機会が増え、自らの言葉で語れるようになっていきます。 また、戦略的目標管理制度を通じて事業部門長と社長が直接向き合い、目標設定や達成状況を 評価する仕組みを作り、「自分たちでやらなければならない」という責任感を、時間をかけて醸成 していきました。
さらに、再生可能エネルギーを導入する際はオンサイトPPAモデルを採用し、工場の屋根を発電 事業者に貸し出して太陽光パネルを設置しました。初期投資を抑えつつ、市場価格より安価に電 力を利用できる仕組みを整え、再エネ100%を達成しています。これにより環境保全がコスト削減 や利益向上に直結する実例を示し、部門の理解を深めました。
非財務を「将来財務」に変えるアプローチ
ESG目標について「将来財務」と表現されていますが、どのような背景でその言葉が導入 されたのでしょうか。
羽田野氏:私たちは現在、持続可能な社会の実現に寄与しながら、自社も持続的に成長すること を目指しています。この取り組みの中で、2020年頃から、事業成長に関連した目標を「財務目 標」、ESGに関連した目標については非財務目標ではなく「将来財務目標」と表現するようにな りました。これは、当時の経営トップから、非財務という呼び方は財務につながらない活動として 軽視されるのではないか、という指摘を受けて考えたものです。
将来財務とは、現在の活動が3〜5年後、あるいは10年後の財務に好影響を与える活動のことを 言います。例えば、リコーではお客様から回収したコピー機を再生して販売する再生機事業に取 り組んできました。当初は赤字が懸念されましたが、回収品質を上げたりリサイクル設計を進め たりと取り組みを進めるうちに、収益性が上がり、10年かけて黒字化を達成しています。このよう な長期的な視点で財務貢献できる活動を「将来財務」と位置づけています。
将来財務に対する取り組みをどのように社内に展開しているのですか?
羽田野氏:当社では、2023年から2025年を対象とした中期経営計画の中で、「事業を通じた社 会課題の解決」と「経営基盤の強化」に関する7つの重要課題を「マテリアリティ」として設 定しました。それぞれの課題には具体的なKPIを設け、16の全社ESG目標、つまり将来財務目 標を策定しています。
これらの全社目標は事業部門ごとに分解され、各部門がESG目標を自主的に設定して事業計 画に組み込むことで、主体的に取り組みを進められるようにしています。また、目標達成度が役 員報酬にも連動する仕組みを導入することで、経営陣が率先して取り組む体制を整えました。
EcoVadis評価を事業成長の指標に
2009年と早くからEcoVadis評価を受審されています。受審のきっかけと、評価の活用方法 について教えてください。
羽田野氏:EcoVadisの評価を受審したのは、欧州の取引先企業からの要請がきっかけです。当 時、特に欧米市場との取引が多く、顧客のニーズに応える形で取り組みを開始しました。受審当 初は、スコア開示を求める企業は年間10社ほどでした。しかし、その重要性は年々高まり、昨年 には欧州企業を中心に84社から要請を受けるまでに拡大しています。
EcoVadisの評価は、欧州をはじめとするサステナビリティ意識の高い市場で、信頼を築く基盤と なっています。そのため、当社では2014年にゴールドメダルを取得したあとも、プラチナメダルの 獲得を目指して取り組みを続けています。
さらに、当社ではEcoVadisを「企業体質改善のための健康診断」として活用しています。評価内 容を通じて課題を洗い出して改善の指針とするだけでなく、設問から社会が企業に期待すること を読み取り、事業戦略や規制対応に反映できるのは受審の大きなメリットです。こうした取り組み により、競争優位性の向上にもつながっていると実感しています。
2040年を見据えたリスクと機会の洗い出し
環境リスクについて、どのように捉え、事業成長に結びつけているのでしょうか。
羽田野氏:現在、当社ではTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)やTNFD(自然関連財 務情報開示タスクフォース)のフレームワークに基づき、リスクと機会を洗い出し、その財務影響 の開示に取り組んでいます。これは、気候変動、資源循環、生物多様性といった環境リスクが、
事業にどのような影響をもたらすのかを分析するものです。例えば当社では、リモートワークの増 加や資源の無駄を省くという消費者行動の変化に伴い、ペーパーレス化が進むことで大きな影 響を受けることがわかっています。
そこでこのリスクを機会として捉えてデジタルサービスへの転換を加速させ、中小企業へのDX支 援に注力することで、環境負荷を削減しつつ1700億円規模の売上を達成しました。今後は、デジ タル分野でのさらなる拡大を目指しています。
また、環境面だけでなく、事業を通じて社会課題解決につなげる社会課題解決型事業を設定 し、その売上目標と実績を開示することで、ESGと事業成長を同時に進めるモデルを確立してい きたいと考えています。
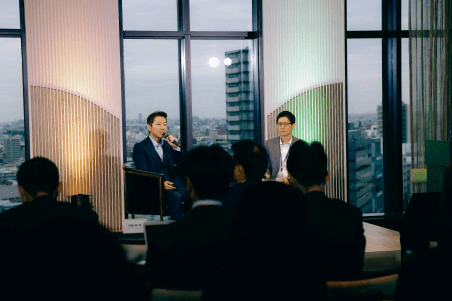
最後に、御社がESGを推進する中で、特に重視されている点について教えてください。
羽田野氏:当社が重視するポイントは4つあります。1つ目は、ESGを経営戦略に統合し、経営の 中心に据えることです。意思決定や目標設定、実績の開示、報酬制度への反映まで、一貫性の ある仕組みを構築することが重要だと考えています。これにより、ESGが経営の中心的要素とし て機能するようになります。
2つ目は、ESG活動を事業成長に結びつけることです。単なる社会貢献ではなく、経営戦略や事 業成長を後押しする要素としてESGを展開し、持続可能な成長の実現を目指しています。
3つ目は、活動の成果を積極的に開示し、ステークホルダーからフィードバックを受け、それをもと に取り組みの改善やレベルアップを図ることです。また、社員一人ひとりが主体的に取り組める 環境を整えることも不可欠です。ESG活動が働きがいやモチベーションにつながる仕組みを構築 することで、社員の積極的な関与を促しています。
4つ目は、地球、社会、経済への持続可能な貢献を企業全体で共有し、推進する企業文化を育 てていくことです。現時点ではまだ課題も残っていますが、この方向性を基盤に、さらなる取り組 みを進めていきたいと考えています。
著者について
Twitterをフォロー LinkedInをフォロー ウェブサイトを訪問する JA EcoVadis JAのコンテンツをもっと見る





















